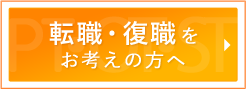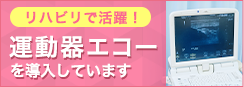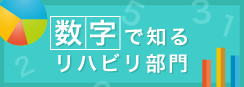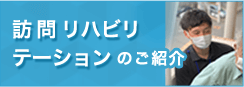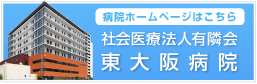ガイドライン推奨の新しい痙縮治療『体外衝撃波治療(ショックウェーブ)』のご紹介2025-11-20【カテゴリー】PTの仕事/リハビリ部 部長より/その他
今回は、脳卒中などの後に起こる痙縮(けいしゅく)の新しい治療法についてご紹介します。
痙縮とは?
痙縮とは、脳損傷や神経系の障害によって、筋肉が緊張しすぎて硬くなってしまう状態を指します。
この状態が続くと、手足が動かしにくくなり、やがて拘縮(こうしゅく)といって関節が固まって動く範囲が狭くなってしまいます。これにより、麻痺の改善が妨げられたり、日常生活動作が困難になったりします。
体外衝撃波治療の有効性
当院では、この痙縮の緩和に役立つ体外衝撃波治療(ショックウェーブ)を導入しています。
この治療法は、一般社団法人日本脳卒中学会が発表した『脳卒中治療ガイドライン2021改訂2025』においても、「痙縮に対して体外衝撃波治療を行うことは妥当である。エビデンスレベル高」と記載されている、非常に有効性の高い治療方法です。
筋肉の緊張や拘縮を緩和することで、患者さんの運動機能の向上や生活の質の改善(QOL向上)が期待されます。
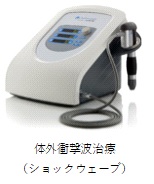
体外衝撃波治療とは?
体外衝撃波治療は、注射や手術を伴わない非侵襲的な物理療法です。緊張が高くなっている筋肉や腱に対し、体外から高出力の音波(衝撃波)を当てることで、硬くなった筋肉の柔軟性を取り戻し、痙縮を和らげることを目指します。
注射によるボツリヌス療法や内服薬といった既存の治療法と並び、痙縮治療の重要な選択肢の一つとして国際的にも注目されています。患者さんへの身体的な負担が少なく、筋緊張の緩和を比較的早期に得られることが大きな特徴です。
当院回復期リハビリテーション病棟での活用
痙縮は、脳卒中発症後、数週間経ってから徐々に現れてくる症状であり、回復期リハビリテーションの時期と重なります。
当院は回復期リハビリテーション病棟として、機能回復に集中的に取り組んでおり、この体外衝撃波治療を積極的に活用しています。主治医の診断のもと、理学療法士が、患者さんの麻痺や症状を詳細に評価し、最も効果的な部位に衝撃波を照射します。特に、患者さんご自身で関節を動かすことが難しい時期にこの治療を行うことで、以下のようなメリットが期待されます。

拘縮の予防:関節が固まる(拘縮)のを予防します。
動作の獲得:治療後のリハビリで、手すりを掴む、スプーンや箸を使うといった日常生活動作(ADL)の獲得に結びつきます。

回復期リハビリテーション病院をお探しの際に、この新しい治療法による当院の積極的な取り組みも参考にしていただければ幸いです。
=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=
社会医療法人有隣会 東大阪病院
リハビリテーション部
・急性期リハビリテーション課
・回復期リハビリテーション課
文責:リハビリテーション部門 部長 椎木
※無断転載禁止
〒536-0005 大阪市城東区中央三丁目4-32
TEL : 06-6939-1125
FAX : 06-6939-7474
Mail: kikaku@yurin.or.jp
TOYOTAが開発した最先端のロボット機器 ウェルウォーク(WW-2000)を導入しました。
=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=
関連記事





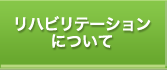




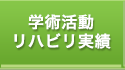

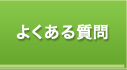
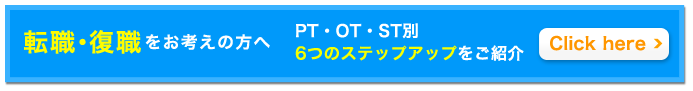

20260205-150x150.jpg)