[病院指標]
令和6年度 病院指標
- 病院指標
- 1.年齢階級別退院患者数
- 2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 5.脳梗塞の患者数等
- 6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
- 医療の質指標
- 1.リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 2.血液培養2セット実施率
- 3.広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 4.転倒・転落発生率
- 5.転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 6.手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- 7.d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 8.65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 9.身体的拘束の実施率
病院指標
1.年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 0 | 35 | 112 | 98 | 139 | 238 | 259 | 566 | 898 | 472 |
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 192 | 28.82 | 20.78 | 15.10% | 87.60 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等 75歳以上 手術なし 手術・処置等2なし | 132 | 23.83 | 16.40 | 7.58% | 86.21 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 92 | 22.32 | 13.66 | 5.43% | 82.29 | |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 62 | 28.10 | 10.26 | 9.68% | 81.16 | |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 61 | 7.36 | 5.55 | 1.64% | 57.57 |
【定義】
令和6年6月~令和7年5月に退院された患者さんを対象にDPCコードの上位5例を診療科別に掲載しています。
在院日数は、当院に入院した日から退院した日までの日数です。(DPC対象病棟以外の病棟も含む)
【解説】
誤嚥性肺炎が最も多く平均年齢が87歳と高齢者に多い疾患であり、平均在院日数も長くなっています。
令和6年6月~令和7年5月に退院された患者さんを対象にDPCコードの上位5例を診療科別に掲載しています。
在院日数は、当院に入院した日から退院した日までの日数です。(DPC対象病棟以外の病棟も含む)
【解説】
誤嚥性肺炎が最も多く平均年齢が87歳と高齢者に多い疾患であり、平均在院日数も長くなっています。
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 40 | 3.95 | 5.55 | 5.00% | 52.83 | |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 手術(K672-2等)あり 手術・処置等2なし | 27 | 5.96 | 7.05 | 0.00% | 60.96 | |
| 060160x001xxxx | 鼠経ヘルニア 15歳以上 手術(K6335等)あり | 22 | 4.95 | 4.54 | 0.00% | 66.73 | |
| 060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 19 | 4.16 | 8.00 | 0.00% | 33.79 | |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 5.43 | 9.08 | 14.29% | 63.93 |
【解説】
令和6年度より外科医3名体制となり、腹腔鏡手術を中心とした症例数が増えています。
腹腔鏡下手術は、手術による切開部を小さくすることができるため、身体的負担を軽減することで、早期退院が可能となります。
令和6年度より外科医3名体制となり、腹腔鏡手術を中心とした症例数が増えています。
腹腔鏡下手術は、手術による切開部を小さくすることができるため、身体的負担を軽減することで、早期退院が可能となります。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 手術(K0811等)あり | 126 | 50.21 | 25.29 | 19.84% | 82.41 | |
| 070370xx99xxxx | 骨粗鬆症 手術なし | 80 | 42.91 | 21.26 | 17.50% | 85.45 | |
| 160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 手術(K0463等)あり | 40 | 14.40 | 17.84 | 7.50% | 49.73 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎,腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし | 38 | 28.39 | 19.16 | 10.53% | 76.16 | |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 手術(K0462等)あり | 32 | 7.38 | 5.95 | 6.25% | 71.25 |
【解説】
当院では高齢者に多くみられる大腿骨骨折の症例が増えています。
当院は急性期病棟、回復期リハビリテーション病棟を有するため、骨粗鬆症や他の慢性疾患をベースにした骨折の患者さんも多く、手術治療後、リハビリが必要な患者様は回復期リハビリテーション病棟で転棟しリハビリを行い、出来る限り早期に社会復帰へとつなげていけるように努力しております。
当院では高齢者に多くみられる大腿骨骨折の症例が増えています。
当院は急性期病棟、回復期リハビリテーション病棟を有するため、骨粗鬆症や他の慢性疾患をベースにした骨折の患者さんも多く、手術治療後、リハビリが必要な患者様は回復期リハビリテーション病棟で転棟しリハビリを行い、出来る限り早期に社会復帰へとつなげていけるように努力しております。
腎臓内科(透析)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 24 | 140.38 | 11.35 | 8.33% | 80.88 | |
| 110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2①「人工腎臓 その他の場合あり」あり | – | – | 13.75 | – | – | |
| 110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術(K6105等)あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 33.81 | – | – | |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2あり②脳血管疾患等リハビリテーション料 定義副傷病なし | – | – | 16.94 | – | – | |
| 040081xx97x0xx | 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし | – | – | 35.71 | – | – |
【解説】
腎臓内科(透析)では、慢性腎臓病(CKD)から透析までの診療を行っています。
早期から腎臓病治療に介入できるよう、地域の先生方との連携をより深めながら、診療体制を充実させています。
※患者数が10未満の場合は、「-」表示となっています。
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StageI | StageII | StageIII | StageIV | 不明 | ||||
| 胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1・2 | 8 |
| 大腸癌 | – | – | – | – | – | – | 1・2 | 8 |
| 乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1・2 | 8 |
| 肺癌 | – | – | – | 10 | – | 20 | 1・2 | 8 |
| 肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1・2 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
【定義】
令和6年6月~令和7年5月に退院された患者さんが対象で、延患者数を集計しています。
DPC対象病棟に入院された患者さんを対象としており、DPC対象病棟から他病棟(障害者病棟、回復期リハビリテーション病棟、緩和ケア病棟)へ転棟した患者さんも含みます。
同じ患者さんが複数回入院された場合もそれぞれ計上しています。
初発とは、当院でがんの診断、初回治療を実施した場合を指します。
再発とは、当院または他院で初回治療が完了した後に、当院で患者さんを診察した場合や、再発・再熱または新たな遠隔転移をきたした場合を指します。
【解説】
当院では、悪性腫瘍の中では肺癌、大腸癌治療を中心に行っています。
当院は他医療機関と連携しており、化学療法や術後の加療目的での受け入れも多く再発件数の割合が高い傾向にあります。
また、当院は緩和ケア病棟を有しており、治療が困難とされた癌患者さんの苦痛を和らげる緩和ケアの体制を整えています。
令和6年6月~令和7年5月に退院された患者さんが対象で、延患者数を集計しています。
DPC対象病棟に入院された患者さんを対象としており、DPC対象病棟から他病棟(障害者病棟、回復期リハビリテーション病棟、緩和ケア病棟)へ転棟した患者さんも含みます。
同じ患者さんが複数回入院された場合もそれぞれ計上しています。
初発とは、当院でがんの診断、初回治療を実施した場合を指します。
再発とは、当院または他院で初回治療が完了した後に、当院で患者さんを診察した場合や、再発・再熱または新たな遠隔転移をきたした場合を指します。
【解説】
当院では、悪性腫瘍の中では肺癌、大腸癌治療を中心に行っています。
当院は他医療機関と連携しており、化学療法や術後の加療目的での受け入れも多く再発件数の割合が高い傾向にあります。
また、当院は緩和ケア病棟を有しており、治療が困難とされた癌患者さんの苦痛を和らげる緩和ケアの体制を整えています。
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 32 | 6.00 | 47.06 |
| 中等症 | 94 | 21.44 | 82.46 |
| 重症 | 22 | 30.50 | 84.32 |
| 超重症 | 1 | 9.00 | 82.00 |
| 不明 | – | – | – |
【定義】
成人とは15歳以上を指し、市中肺炎とは普段の生活の中で罹患した肺炎を指します。
令和6年6月~令和7年5月に退院された患者さんが対象です。
DPC対象病棟に入院された患者さんを対象としており、DPC対象病棟から他病棟(障害者病棟、回復期リハビリテーション病棟、緩和ケア病棟)へ転棟した患者さんも含みます。
重症度は市中肺炎ガイドラインによる重症度分類システム(A-DROPシステム)により分類しています。
下記のうち該当項目数によって重症度が分類されます。
≪A-DROPシステム≫
1.男性70歳以上、女性75歳以上
2.BUN21dL以上または脱水あり
3.酸素飽和度90%以下
4.意識障害
5.収縮期血圧90㎜Hg以下
※軽症:0項目 中等度:1~2項目 重症:3項目 超重症:4~5項目、ただし、意識障害(ショック)であれば1項目でも超重症
【解説】
症例数では中等度の割合が最も多く、全体の7割を超えています。
患者さんの年齢層が高く、慢性呼吸器疾患の併存症をお持ちの方も多いことで、在院日数が長期化する一因となっています。
成人とは15歳以上を指し、市中肺炎とは普段の生活の中で罹患した肺炎を指します。
令和6年6月~令和7年5月に退院された患者さんが対象です。
DPC対象病棟に入院された患者さんを対象としており、DPC対象病棟から他病棟(障害者病棟、回復期リハビリテーション病棟、緩和ケア病棟)へ転棟した患者さんも含みます。
重症度は市中肺炎ガイドラインによる重症度分類システム(A-DROPシステム)により分類しています。
下記のうち該当項目数によって重症度が分類されます。
≪A-DROPシステム≫
1.男性70歳以上、女性75歳以上
2.BUN21dL以上または脱水あり
3.酸素飽和度90%以下
4.意識障害
5.収縮期血圧90㎜Hg以下
※軽症:0項目 中等度:1~2項目 重症:3項目 超重症:4~5項目、ただし、意識障害(ショック)であれば1項目でも超重症
【解説】
症例数では中等度の割合が最も多く、全体の7割を超えています。
患者さんの年齢層が高く、慢性呼吸器疾患の併存症をお持ちの方も多いことで、在院日数が長期化する一因となっています。
5.脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| – | 13 | 57.54 | 82.69 | 38.46% |
【定義】
令和6年6月~令和7年5月に退院された患者さんが対象です。
DPC対象病棟に入院された患者さんを対象としており、DPC対象病棟から他病棟(障害者病棟、回復期リハビリテーション病棟、緩和ケア病棟)へ転棟した患者さんも含みます。
在院日数は、当院に入院した日から退院した日までの日数です。(DPC対象病棟以外の病棟も含む)
「ICD10」とは、疾病及び関連保健問題の国際統計分類です。WHOによって公表された分類で、死因や疾病の統計、診療記録の管理などに活用されます。疾病のアルファベットと数字によって表しています。
【解説】
当院では回復期リハビリテーション病棟を併設しており急性期治療後のリハビリにも積極的に行っていますので平均在院日数は一般病棟よりも長くなっています。
令和6年6月~令和7年5月に退院された患者さんが対象です。
DPC対象病棟に入院された患者さんを対象としており、DPC対象病棟から他病棟(障害者病棟、回復期リハビリテーション病棟、緩和ケア病棟)へ転棟した患者さんも含みます。
在院日数は、当院に入院した日から退院した日までの日数です。(DPC対象病棟以外の病棟も含む)
「ICD10」とは、疾病及び関連保健問題の国際統計分類です。WHOによって公表された分類で、死因や疾病の統計、診療記録の管理などに活用されます。疾病のアルファベットと数字によって表しています。
【解説】
当院では回復期リハビリテーション病棟を併設しており急性期治療後のリハビリにも積極的に行っていますので平均在院日数は一般病棟よりも長くなっています。
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K664 | 経皮的内視鏡下胃瘻増設術(経鼻) | 19 | 33.63 | 108.63 | 26.32% | 85.32 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 17 | 3.53 | 18.18 | 5.88% | 71.41 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術(直径2㎝未満) | 10 | 12.7 | 15.6 | 0.00% | 76.40 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
| K722 | 小腸・結腸内視鏡的止血術 | – | – | – | – | – |
【定義】
令和6年6月~令和7年5月に退院された患者さんが対象です。
DPC対象病棟に入院された患者さんを対象としており、DPC対象病棟から他病棟(障害者病棟、回復期リハビリテーション病棟、緩和ケア病棟)へ転棟した患者さんも含みます。
手術方式の点数表コード(Kコード)によって集計しています。
10症例以上を集計対象とし、1入院中で主要な手術1つのみを症例数に集計しているため、手術の実施件数と必ずしも一致するとは限りません。
【解説】
内科では、ポリープ切除術以外でも胆管炎等に有効である内視鏡的胆道ステント留置術も積極的に行っています。
※患者数が10未満の場合は、「-」表示となっています。
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 36 | 1.67 | 4.67 | 0.00% | 60.67 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 22 | 1.36 | 3.23 | 0.00% | 67.50 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 10 | 1.20 | 3.40 | 0.00% | 48.40 | |
| K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | – | – | – | – | – | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | – | – | – | – | – |
【解説】
令和6年度より外科医3名体制となり、腹腔鏡手術を中心とした症例数が増えています。
腹腔鏡下手術は、手術による切開部を小さくすることができるため、身体的負担を軽減することで、早期退院が可能となります。
※患者数が10未満の場合は、「-」表示となっています。
令和6年度より外科医3名体制となり、腹腔鏡手術を中心とした症例数が増えています。
腹腔鏡下手術は、手術による切開部を小さくすることができるため、身体的負担を軽減することで、早期退院が可能となります。
※患者数が10未満の場合は、「-」表示となっています。
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿)(上腕) | 105 | 3.25 | 38.96 | 16.19% | 79.70 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 79 | 4.62 | 59.66 | 16.46% | 82.09 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(下腿)(前腕) | 73 | 2.49 | 12.37 | 9.59% | 62.66 | |
| K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨)(膝蓋骨)(手・足) | 48 | 1.83 | 8.23 | 4.17% | 56.15 | |
| K0821 | 人工関節置換術(膝)(股) | 46 | 1.33 | 33.39 | 2.17% | 71.87 |
【解説】
骨折手術を多数行っており、中でも高齢者の方に多い大腿骨骨折の手術件数を多く行っています。継続してリハビリが必要な患者様は、併設の回復期リハビリテーション病棟へ転床し治療致しますので、術後の日数が長期となっています。
また、専門医による人工関節置換術も増加しています。
骨折手術を多数行っており、中でも高齢者の方に多い大腿骨骨折の手術件数を多く行っています。継続してリハビリが必要な患者様は、併設の回復期リハビリテーション病棟へ転床し治療致しますので、術後の日数が長期となっています。
また、専門医による人工関節置換術も増加しています。
腎臓内科(透析)
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 25 | 91.96 | 188.60 | 16.00% | 81.32 | |
| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | – | – | – | – | – | |
| K616-8 | 吸着式潰瘍治療法 | – | – | – | – | – |
【解説】
腎臓内科では、透析治療に利用するシャントのトラブルや設置の手術の他にも、透析患者様に定期的な検査を実施することで合併症の早期発見、早期治療を心掛けています。
※患者数が10未満の場合は、「-」表示となっています。
腎臓内科では、透析治療に利用するシャントのトラブルや設置の手術の他にも、透析患者様に定期的な検査を実施することで合併症の早期発見、早期治療を心掛けています。
※患者数が10未満の場合は、「-」表示となっています。
7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | 0.00% |
| 異なる | – | 0.18% | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | – | 0.25% |
| 異なる | – | 0.32% | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | 0.11% |
| 異なる | – | 0.04% |
【定義】
令和6年6月~令和7年5月に退院された患者さんが対象です。
DPC対象病棟に入院された患者様を対象としており、DPC対象病棟から他病棟(障害者病棟、回復期リハビリテーション病棟、緩和ケア病棟)へ転棟した患者さんも含みます。
10未満の数値は、-(ハイフン)で表示しています。
【解説】
医療の質の改善に資するため、臨床上ゼロになりえないものの少しでも改善すべきものとして重篤な疾患である敗血症、播種性血管内凝固、その他の真菌症、手術処置の合併症について、入院契機病名(入院のきっかけとなった傷病)の同一性の有無を区別して対象患者数と発症率を示したものです。
当院の手術処置の合併症は人工透析をおこなう為に作った人工血管に付随する狭窄や閉塞がほとんどです。
手術・処置等の合併症についての内訳は、下記の傷病名となります。
内訳(生検後出血、カテーテル関連尿路感染症)
※症例数が10未満の場合は、「-」表示となっています。
令和6年6月~令和7年5月に退院された患者さんが対象です。
DPC対象病棟に入院された患者様を対象としており、DPC対象病棟から他病棟(障害者病棟、回復期リハビリテーション病棟、緩和ケア病棟)へ転棟した患者さんも含みます。
10未満の数値は、-(ハイフン)で表示しています。
【解説】
医療の質の改善に資するため、臨床上ゼロになりえないものの少しでも改善すべきものとして重篤な疾患である敗血症、播種性血管内凝固、その他の真菌症、手術処置の合併症について、入院契機病名(入院のきっかけとなった傷病)の同一性の有無を区別して対象患者数と発症率を示したものです。
当院の手術処置の合併症は人工透析をおこなう為に作った人工血管に付随する狭窄や閉塞がほとんどです。
手術・処置等の合併症についての内訳は、下記の傷病名となります。
内訳(生検後出血、カテーテル関連尿路感染症)
※症例数が10未満の場合は、「-」表示となっています。
医療の質指標
1.リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 364 | 330 | 90.66% |
【解説】
肺血栓塞栓症は、主に下肢の静脈の深部にできた血栓(深部静脈血栓症と呼ばれます)がはがれて血流によって運ばれ、肺動脈に閉塞を引き起こしてしまう疾患です。
肺血栓塞栓症は、血栓の大きさや血流の障害の程度によって軽症から重症までのタイプがあります。血栓によって太い血管が閉塞してしまうような重篤な場合には、肺の血流が途絶し、酸素が取り込めなくなり、ショック状態から死に至ることもあります。
近年、深部静脈血栓症や肺血栓塞栓症の危険因子が明らかになってきています。
発症に至る前に危険レベルに応じた予防対策を行うことが一般的に推奨されており、当院での実施率を示しました。
リスクレベル「中」以上と定義される患者さんの約9割に弾性ストッキング・抗凝固療法いずれかの予防対策を実施していますが、出血リスクが高く抗凝固剤を使用できない場合など、予防対策を実施できないこともあります。
肺血栓塞栓症は、主に下肢の静脈の深部にできた血栓(深部静脈血栓症と呼ばれます)がはがれて血流によって運ばれ、肺動脈に閉塞を引き起こしてしまう疾患です。
肺血栓塞栓症は、血栓の大きさや血流の障害の程度によって軽症から重症までのタイプがあります。血栓によって太い血管が閉塞してしまうような重篤な場合には、肺の血流が途絶し、酸素が取り込めなくなり、ショック状態から死に至ることもあります。
近年、深部静脈血栓症や肺血栓塞栓症の危険因子が明らかになってきています。
発症に至る前に危険レベルに応じた予防対策を行うことが一般的に推奨されており、当院での実施率を示しました。
リスクレベル「中」以上と定義される患者さんの約9割に弾性ストッキング・抗凝固療法いずれかの予防対策を実施していますが、出血リスクが高く抗凝固剤を使用できない場合など、予防対策を実施できないこともあります。
2.血液培養2セット実施率
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 278 | 213 | 76.62% |
【解説】
血液は本来無菌であり、血液中から細菌が検出される場合は重篤な感染症が疑われます。
感染症が疑われる場合、その原因菌を突き止めるため血液培養を行いますが、血液中に含まれる微生物の数は非常に少ないため、通常の採血よりも多くの血液を採取する必要があります。
培養ボトルへの採取は嫌気性菌用と好気性菌用の2本で1セットとし、1セット採取で20ml、2セット採取では40mlの血液が必要です。
血液培養は1セット採取では原因菌の検出率が73%ですが、2セット採取すると90%になるといわれており2セット採取することで検出率の向上が期待できます。さらに、この2セット採取を異なる場所から1セットずつ採取すれば、検出された菌が原因菌か消毒の不備などによる外部からの菌の混入(コンタミネーション)かの区別がつきやすくなります。
上記の効果を得るため2セット実施率を上げることを目標としています。
血液は本来無菌であり、血液中から細菌が検出される場合は重篤な感染症が疑われます。
感染症が疑われる場合、その原因菌を突き止めるため血液培養を行いますが、血液中に含まれる微生物の数は非常に少ないため、通常の採血よりも多くの血液を採取する必要があります。
培養ボトルへの採取は嫌気性菌用と好気性菌用の2本で1セットとし、1セット採取で20ml、2セット採取では40mlの血液が必要です。
血液培養は1セット採取では原因菌の検出率が73%ですが、2セット採取すると90%になるといわれており2セット採取することで検出率の向上が期待できます。さらに、この2セット採取を異なる場所から1セットずつ採取すれば、検出された菌が原因菌か消毒の不備などによる外部からの菌の混入(コンタミネーション)かの区別がつきやすくなります。
上記の効果を得るため2セット実施率を上げることを目標としています。
3.広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 370 | 223 | 60.27% |
【解説】
細菌培養検査は感染症の原因菌を特定するために実施します。
細菌培養検査を実施することで、病原体に対して感受性のある(効く)抗菌薬を知ることが出来ます。抗菌薬投与前に細菌培養検査を実施していれば、病原微生物が耐性菌の場合にも効果のある抗菌薬を選択することが出来ます。
このため、細菌培養検査の提出率を見ることは抗菌薬適正使用の指標のひとつとなり、提出率は高い方が望ましいです。
投与されている抗菌薬の数に関わらず1つの感染症に対して細菌培養検査が提出されているかどうかを見ています。
細菌培養検査は感染症の原因菌を特定するために実施します。
細菌培養検査を実施することで、病原体に対して感受性のある(効く)抗菌薬を知ることが出来ます。抗菌薬投与前に細菌培養検査を実施していれば、病原微生物が耐性菌の場合にも効果のある抗菌薬を選択することが出来ます。
このため、細菌培養検査の提出率を見ることは抗菌薬適正使用の指標のひとつとなり、提出率は高い方が望ましいです。
投与されている抗菌薬の数に関わらず1つの感染症に対して細菌培養検査が提出されているかどうかを見ています。
4.転倒・転落発生率
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 53,238 | 336 | 6.31 |
【解説】
転倒とは患者自身の意思を問わずに床に足底以外の場所がつく状態のことです。転倒は、麻痺や筋力低下などの身体要因、認知症による判断力の低下などの要因、手術の影響、薬剤の影響、患者を取り巻く環境などの様々な要因が複合的に作用して起こります。当院では、すべての入院患者さんに対し、入院時、入院24時間経過後とそれ以降定期的に転倒・転落リスクアセスメントを実施しています。さらに、状態変化時、術後、転倒・転落事例発生時にも再評価と、個別の看護計画に基づいた予防策を講じています。リスク評価を行い、予防策を実施して低い値を目指し患者安全の確保に努めてまいります。
転倒とは患者自身の意思を問わずに床に足底以外の場所がつく状態のことです。転倒は、麻痺や筋力低下などの身体要因、認知症による判断力の低下などの要因、手術の影響、薬剤の影響、患者を取り巻く環境などの様々な要因が複合的に作用して起こります。当院では、すべての入院患者さんに対し、入院時、入院24時間経過後とそれ以降定期的に転倒・転落リスクアセスメントを実施しています。さらに、状態変化時、術後、転倒・転落事例発生時にも再評価と、個別の看護計画に基づいた予防策を講じています。リスク評価を行い、予防策を実施して低い値を目指し患者安全の確保に努めてまいります。
5.転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
|---|---|---|
| 53,238 | 6 | 0.11 |
【解説】
転倒転落によりケガなどが発生した場合、なかでも傷害の程度が高い転倒転落の発生率です。影響度分類とは、医療機関内で発生したインシデントを、患者さんへ臨床的影響に基づき段階的に評価するものです。当院では医療安全指針に基づき、影響度をレベル0(影響なし)からレベル5(死亡)まで分類し、インシデントの分析と再発防止策の立案に活用しています。レベル3bは、事象により濃厚な医療介入を要する事例を指します。治療を最優先しながら、発生した転倒・転落事例に対し患者安全の確保を優先したリスクアセスメント再評価と、個別の看護計画に基づいた予防策を講じてまいります。
転倒転落によりケガなどが発生した場合、なかでも傷害の程度が高い転倒転落の発生率です。影響度分類とは、医療機関内で発生したインシデントを、患者さんへ臨床的影響に基づき段階的に評価するものです。当院では医療安全指針に基づき、影響度をレベル0(影響なし)からレベル5(死亡)まで分類し、インシデントの分析と再発防止策の立案に活用しています。レベル3bは、事象により濃厚な医療介入を要する事例を指します。治療を最優先しながら、発生した転倒・転落事例に対し患者安全の確保を優先したリスクアセスメント再評価と、個別の看護計画に基づいた予防策を講じてまいります。
6.手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 579 | 578 | 99.83% |
【解説】
予防的抗菌薬投与率は、手術部位感染(SSI)の発生を減らすために、手術前に抗菌薬を投与する割合です。手術執刀開始の1時間以内に、適切な抗菌薬を静注することで、SSIを予防し、入院期間の延長や医療費の増大を抑えることができると考えられています。
手術執刀開始の1時間以内に適切な抗菌薬を静注射することでSSIの発生リスクの低減に努めています。
当院では全身麻酔手術で予防的抗菌薬投与が実施された手術のうち、99.83%の手術が手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬投与が実施されております。
予防的抗菌薬投与率は、手術部位感染(SSI)の発生を減らすために、手術前に抗菌薬を投与する割合です。手術執刀開始の1時間以内に、適切な抗菌薬を静注することで、SSIを予防し、入院期間の延長や医療費の増大を抑えることができると考えられています。
手術執刀開始の1時間以内に適切な抗菌薬を静注射することでSSIの発生リスクの低減に努めています。
当院では全身麻酔手術で予防的抗菌薬投与が実施された手術のうち、99.83%の手術が手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬投与が実施されております。
7.d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 53,187 | 19 | 0.03 |
【解説】
褥瘡は、医療の質評価の重要な指標の1つとなっており、本項目はd2(真皮までの損傷以上)の褥瘡の発生率を示しています。褥瘡とは低栄養の患者さんが自力で体位交換ができず、長期間の寝たきりになるなどにより、圧迫されている場所の血流が悪くなることで、皮膚に傷ができてしまうことをいい、一般的には「床ずれ」ともいわれます。当院では多職種による褥瘡対策委員会が組織され、ハイリスクの患者さんに対しての褥瘡予防計画の立案や、発生時には回診を行い早期の治癒を目指しています。
褥瘡は、医療の質評価の重要な指標の1つとなっており、本項目はd2(真皮までの損傷以上)の褥瘡の発生率を示しています。褥瘡とは低栄養の患者さんが自力で体位交換ができず、長期間の寝たきりになるなどにより、圧迫されている場所の血流が悪くなることで、皮膚に傷ができてしまうことをいい、一般的には「床ずれ」ともいわれます。当院では多職種による褥瘡対策委員会が組織され、ハイリスクの患者さんに対しての褥瘡予防計画の立案や、発生時には回診を行い早期の治癒を目指しています。
8.65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
| 65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 1,910 | 1,902 | 99.58% |
【解説】
当院の栄養課では、入院患者ほぼ全てに対して入院初日に栄養スクリーニング(MNA)、低栄養診断であるGLIM基準を実施し、多職種(医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、セラピストなど)による栄養管理計画書を作成しています。当院は65歳以上の高齢の患者が多いので、早期に低栄養のリスクを評価し適切な介入をすることで、治療の促進に努めています。
当院の栄養課では、入院患者ほぼ全てに対して入院初日に栄養スクリーニング(MNA)、低栄養診断であるGLIM基準を実施し、多職種(医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、セラピストなど)による栄養管理計画書を作成しています。当院は65歳以上の高齢の患者が多いので、早期に低栄養のリスクを評価し適切な介入をすることで、治療の促進に努めています。
9.身体的拘束の実施率
| 退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
| 53,238 | 6,312 | 11.86% |
【解説】
身体拘束実施率とは、一定期間内に入院した患者さんの延べ人数に対して、身体拘束を受けた患者さんの割合を示す指標です。
当院では、患者さんの安全を確保しつつ、その尊厳を尊重するため、身体拘束の最小化に積極的に取り組んでいます。
身体拘束は、患者さんの心身の自由を制限し、尊厳を損なう行為です。そのため、生命や身体の保護を目的とした緊急かつやむを得ない場合を除き、原則として行いません。
この理念に基づき、当院では職員全体の意識を共有するため、定期的な研修を通じて教育を徹底しています。また、多職種の専門家が集まるカンファレンスを定期的に開催し、身体拘束の代替方法や拘束時間の短縮について議論を重ねています。さらに、認知症の患者さんには、個別のニーズに応じたケアを提供することで、不穏な行動を落ち着かせ、身体拘束を必要としない環境づくりに努めています。
身体拘束実施率を一つの指標として取り組みの成果を客観的に評価していますが、数字だけでなく、職員一人ひとりの意識の変化と、日々の丁寧なケアを大切にしています。今後も、患者さんの安全と尊厳を守るため、転倒やチューブ類の自己抜去といったリスク管理と、身体拘束の最小化のバランスを慎重に見極めながら、より良い医療の提供に努めてまいります。
身体拘束実施率とは、一定期間内に入院した患者さんの延べ人数に対して、身体拘束を受けた患者さんの割合を示す指標です。
当院では、患者さんの安全を確保しつつ、その尊厳を尊重するため、身体拘束の最小化に積極的に取り組んでいます。
身体拘束は、患者さんの心身の自由を制限し、尊厳を損なう行為です。そのため、生命や身体の保護を目的とした緊急かつやむを得ない場合を除き、原則として行いません。
この理念に基づき、当院では職員全体の意識を共有するため、定期的な研修を通じて教育を徹底しています。また、多職種の専門家が集まるカンファレンスを定期的に開催し、身体拘束の代替方法や拘束時間の短縮について議論を重ねています。さらに、認知症の患者さんには、個別のニーズに応じたケアを提供することで、不穏な行動を落ち着かせ、身体拘束を必要としない環境づくりに努めています。
身体拘束実施率を一つの指標として取り組みの成果を客観的に評価していますが、数字だけでなく、職員一人ひとりの意識の変化と、日々の丁寧なケアを大切にしています。今後も、患者さんの安全と尊厳を守るため、転倒やチューブ類の自己抜去といったリスク管理と、身体拘束の最小化のバランスを慎重に見極めながら、より良い医療の提供に努めてまいります。



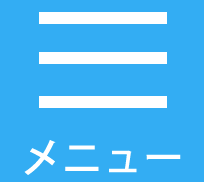
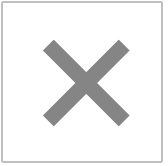




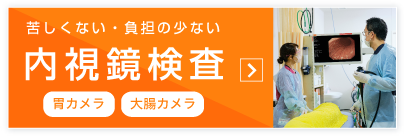
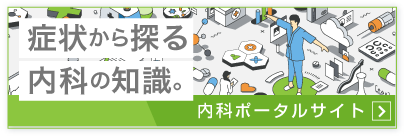



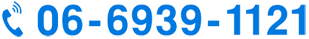
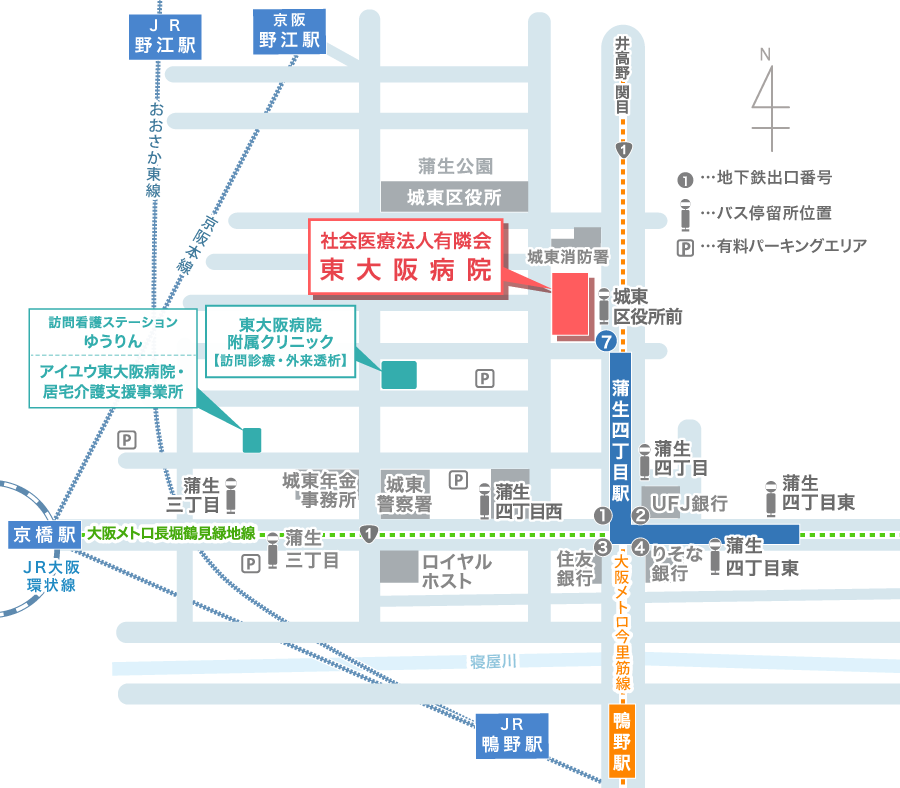
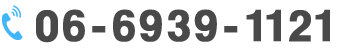
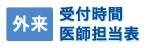

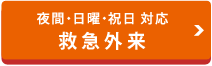
このページの中で公開している当院の病院指標はすべて、令和6年度(令和6年6月1日から令和7年5月31日まで)の退院症例から算出しています。集計の対象は、健康保険を使用した入院症例のみで、労災、自賠責保険、自由診療の症例は含まれておりません。
また、当院の障害者病棟、回復期リハビリテーション病棟、緩和ケア病棟にのみ入院の症例、そして入院した後24時間以内に死亡した症例も集計対象外としております。
年齢は入院した時点での年齢で集計し、10未満の数値の場合は-(ハイフン)で表示しています。
【解説】
当院を利用している患者さんは80歳代が一番多く、全体の約32%を占めています。
また、70歳以上の患者さんの割合が全体の約69%を占め、地域社会の高齢化を反映しています。