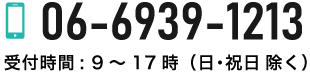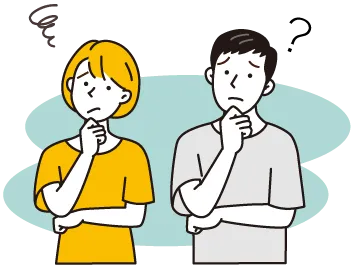『人間ドック』の語源は?
2025-7-25
「人間ドック」の語源と発展
「人間ドック」という言葉は、単に船のドックに由来するというだけでなく、その誕生には当時の社会背景や医療の進展が深く関わっています。

船の「ドック」が持つ意味合い
まず、語源となった「ドック」について掘り下げてみましょう。ドックとは、船体を陸に上げて、普段は見ることのできない船底や内部を徹底的に検査・修理するための施設です。航海の安全を確保するために、船は定期的にドック入りし、細部にわたる点検や必要な修繕が行われます。
この「ドック」の持つ意味合いは、以下の3つの点で「人間ドック」に通じるものがあります。
▶徹底的な点検: 普段の運航(日常生活)では見過ごされがちな部分まで、細かくチェックする。
▶早期発見・早期治療: 不具合が見つかれば、それが深刻になる前に修理・改善する。
▶安全の確保: 大規模な事故や故障を防ぎ、将来にわたる機能維持を目指す。
「人間ドック」の誕生と普及
「人間ドック」という言葉が誕生し、普及した背景には、日本の高度経済成長期における健康意識の変化と医療技術の進歩があります。
戦後の復興と経済成長: 戦後、日本は急速な経済成長を遂げ、人々の生活水準が向上しました。しかし、一方で生活習慣病の増加など、新たな健康問題も顕在化し始めました。
成人病の概念の登場: 1950年代後半から1960年代にかけて、「成人病」という概念が提唱され、脳卒中、心臓病、がんなどの病気が、それまでの感染症とは異なる、生活習慣に起因する病気として認識されるようになりました。これらの病気は自覚症状がないまま進行することが多く、早期発見の重要性が叫ばれるようになりました。
医療技術の進歩: X線検査、心電図、血液検査などの診断技術が進歩し、比較的短期間で全身の健康状態を評価することが可能になりました。
このような背景の中で、「病気になる前に、定期的に全身をくまなく検査し、病気の芽を摘み取ろう」という予防医学の考え方が広まりました。
そして、1954年に国立東京第一病院(現:国立国際医療研究センター病院)が日本で初めて「人間ドック」という名称での健診を開始しました。この「人間ドック」という名称は、当時の国立東京第一病院の院長であった土屋文雄氏が、船のドックにヒントを得て名付けたと言われています。
和製英語としての定着
「人間ドック」は、英語圏では”medical check-up”や”comprehensive health examination”などと表現され、「人間ドック」という言葉はそのままでは通じません。これは、まさに日本独自の文化と医療の発展の中で生まれた「和製英語」であり、その概念とともに日本社会に深く根付いた言葉と言えます。
このように、「人間ドック」という言葉は、単なる医療行為の名称に留まらず、日本の予防医学の歴史と、国民の健康意識の変遷を象徴する言葉なのです。